講義を担当したのは、一般社団法人「読み書き配慮」代表理事・菊田史子氏。
学習障害をもつ子どもを育て上げた経験をきっかけに、読み書きに困難を抱える子どもたちをICTで支援する取り組みを全国に広めています。ICT機器の利用が、子どもたちの学びの可能性を広げることを実体験をもとに説明しました。
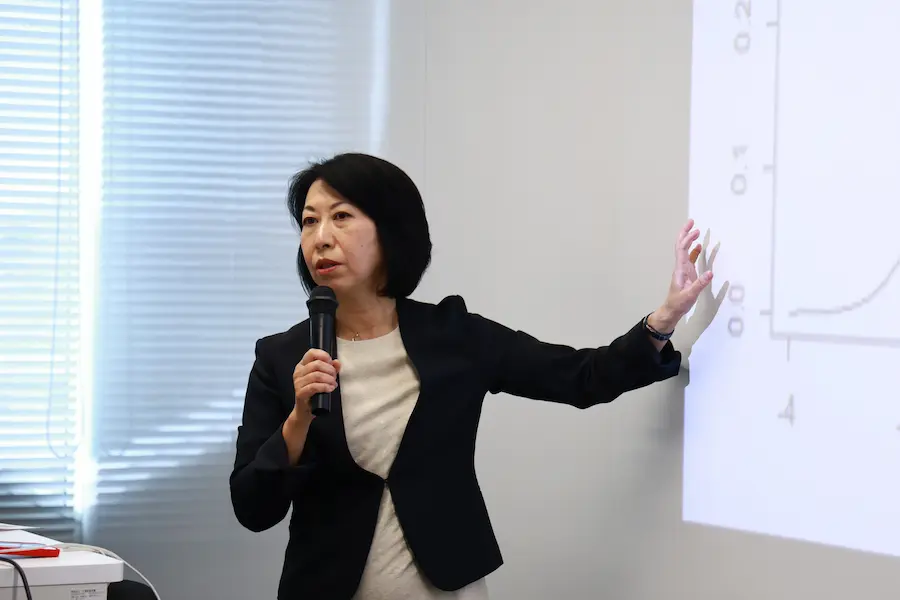
「読み書きができる=勉強ができる」とは言えません。文字を読むのに時間がかかったり、板書を写すのがちょっと大変だったりしても、理解する力や考える力をもっている子どもは少なくありません。そんな子どもたちが学びやすい環境を整えるには、その子に合った学び方を選べるようにしていくことが重要です。こうした視点は、これから学校現場に向かう4年生にとって、欠かせません。
「教職実践演習」では、教育実習を終えた4年生が、自分に必要な学びを整理しながら、教員としての準備を進めていきます。今回の特別講義では、読み書きの困難やICTの活用をテーマに、子どもの学びをどのように支えるかを考えました。
講義を担当したのは、一般社団法人「読み書き配慮」代表理事・菊田史子氏。
学習障害をもつ子どもを育て上げた経験をきっかけに、読み書きに困難を抱える子どもたちをICTで支援する取り組みを全国に広めています。ICT機器の利用が、子どもたちの学びの可能性を広げることを実体験をもとに説明しました。
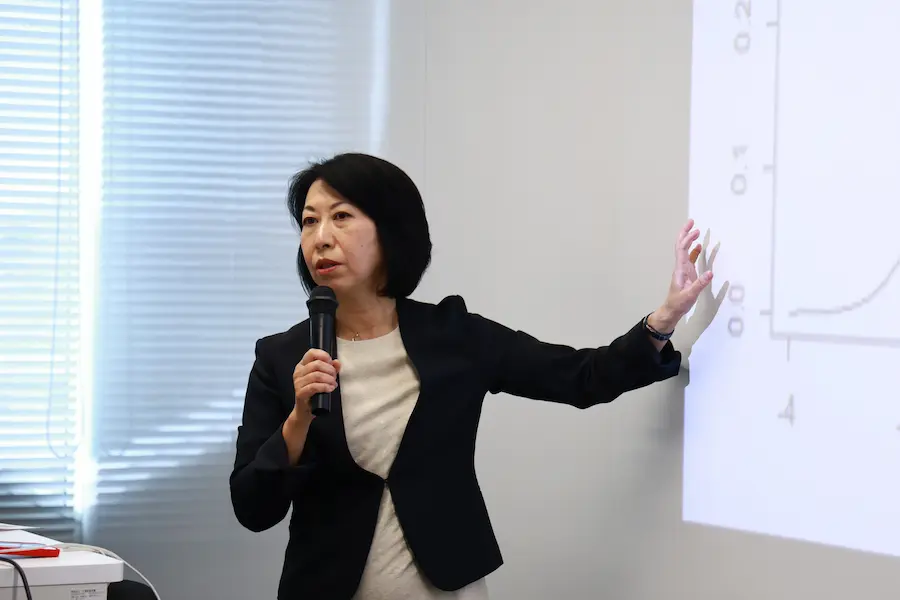
「35人学級だと3人」特別な教育的支援が必要な子どもの割合です。その中には学習障害(知的な発達に遅れは無いが、読み書きや計算など特定の課題のみ苦手)がある子どもたちも含まれます。
読み書きが困難な子どもにとっては、教科書を音読する・問題をノートに書く・漢字を練習するなど学校現場であたりまえとされていることが、高い壁になることもあります。答えのない課題に向かう力や、自分の考えを広げていく力は、必ずしも“鉛筆と紙の学習”だけで身につくものではありません。PCやタブレットなど、ICTを使った学び方も大切な選択肢であり、「読み書きができる=勉強ができる」ではない という視点が改めて強調されました。
後半では、読み書き困難な子どもたちを支援する「KIKUTAプログラム」も紹介されました。プログラムには、ICTを使って“できた”を積み重ねる経験や、自分に必要な配慮を自分で伝える力を育てる取り組みなど、子どもたちが自信をもって学べるための工夫が盛り込まれています。
講演全体を通して、学生たちは「学び方は一つではない」という視点に気づき、子どもに寄り添うためのヒントを多く得られたようでした。

「学校で育てたい力」はどんな力か考えます。

「学習障害の子どもに教員としてどのような支援ができるか」という質問がありました。
講演会後は、小林ゼミの学生を中心に少人数での懇談会を開きました。講演での気づきを踏まえ、学生からはさまざまな質問が出てきました。
懇談会で特に話題になったのが「書写」の指導についての質問でした。ある学生は、自分自身が字を書くことに苦手意識があり、作品を掲示されるのがつらかった経験をふまえ、「書写は書くことが苦手な子にとってとてもハードルが高いのではないか」と質問を投げかけました。
学習指導要領では、3年生から毎年毛筆の授業を行い、文字を“正しく整えて書くこと”が求められています。読み書き困難がある子どもにとって負担が大きくなりやすく、ICTを使ったとしても指導のイメージがつかみにくい点は、学生たちも共通して感じていたようです。この問いをきっかけに、書写の目的や評価のあり方、授業での工夫など、さまざまな視点から意見が交わされました。明確な答えが出るテーマではありませんが、書写という身近な教科だからこそ、子どものつまずきにどう寄り添うかを考えるきっかけになりました。


今回の特別講義は、子どもたちの学び方の多様性に目を向け、どのように学習を支えられるかを考える貴重な機会でした。次回の授業では、学生たちがグループに分かれ、学校現場でのICT活用例を調べて共有し合う予定です。
これから教育現場に立つ学生たちが一人ひとりの子どもに寄り添い、その子に合った学び方を支えられる教員へと成長していくことを期待しています。