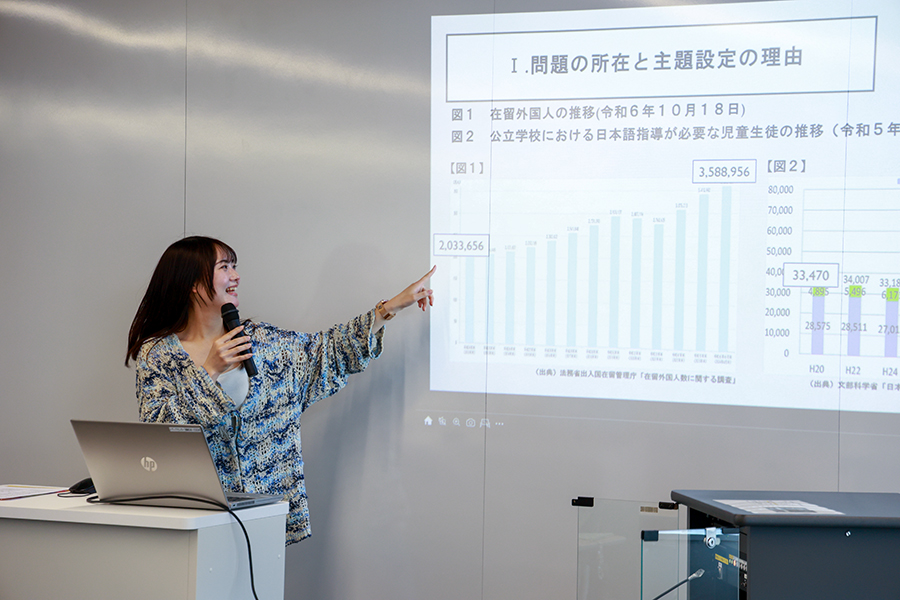Jさんは防災教育について研究しています。先行研究では、災害の恐怖を強調しすぎると子どもたちが思考停止に陥り「防災嫌い」になってしまう一方、楽しさだけを追求すると肝心な学びが抜け落ちて「見せかけの防災」になってしまうことが指摘されています。そこで、Jさんは遊びと学びを両立した「あそぼうさい」に着目。既存の高価格な教材を簡略化し、予算の限られる教育現場でも簡単に導入できるよう調査と改善を進めています。
実際にJさんは、自身の所属する敬愛大学のクラブ・サークル(教育ボランティアIris)で、富里市の児童37名と保護者20名を対象に防災イベントを企画・実施しました。学生による寸劇を交えながら「防災バッグづくり」や「簡易トイレ体験」、「水消火器の的あてゲーム」などを実施。参加者が楽しみながら防災スキルを体験できる工夫が凝らされました。
イベント後のアンケートでは、参加した児童の多くが「とても楽しかった」と回答し、学生スタッフも全員が楽しかったと答えるなど、参加者・運営者双方の満足度が高かったことが示されました。一方で、児童の感想の中に「学びになった」という声はあったものの、「日常生活に生かそうとする意見はほとんどなかった」という新たな課題を発見しました。また、水消火器の的当てゲームでは消防署から無償で借りられたものの、水の補充後は水圧が足りず、活動に支障が出てしまいました。
この結果からJさんは、イベントでの楽しさや学びを、いざという時の「自分ごと」として捉え、実際の行動に繋げるための工夫がさらに必要だと考察しています。今後は、特別支援学校での防災教育についても視野に入れ、低・中・高学年それぞれの発達段階に応じた、より実践的な「あそぼうさい」プランを具体的に提案していく予定です。